死の淵で見た生きる意味
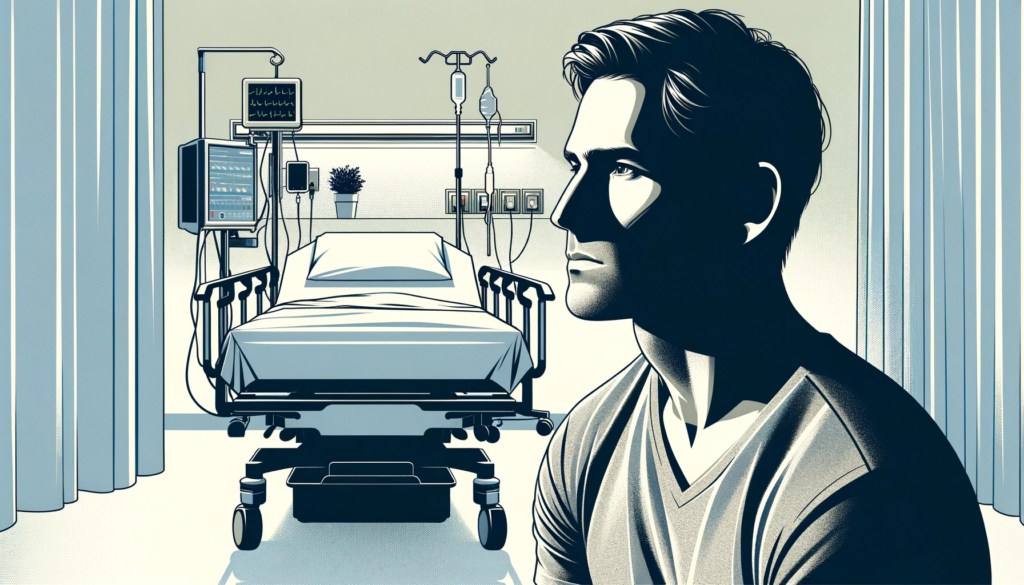
闇は耳から明けた。
「おい、おまえたち、なにをのろのろやってんだ。テキパキ動けよ。でなきゃこの患者、死ぬぞ!」
この声は……確か「古市」と名乗った副院長のものだ。いや「古川」だったか。自分自身の状況さえちゃんと把握できていないのに、怒鳴り続けている男の名前のたしかさに拘っている自分の思考を自嘲気味に認識する。
「先生、うるさいよ。そんな大声を出されると、とても寝てられない」
自分の声があまりにも細く、力が籠もらないことを自覚する。そうか。終わったのか。つまり、ここは東京ハート国際病院のICUだ。
「ああ、目覚めたんですね」
ナースがベッドに近づき、機器の数値を確認している。
「いま、何時?」
「夜の10時です」
朝の8時に手術室に入ったので、あれから14時間が経ったわけである。
「ああ、喉が渇いた」
突如襲ってきた渇きに、ナースから「食べすぎないように」と嗜められながらも、欲望のままに次々と氷を口に入れた。噛み砕く時間さえもどかしい。ガリガリと大袈裟な音を立てて崩れる氷の冷たさが、口に、喉に、胸に伝わっていく。
生きている。俺は生きている。
冷えた口内を舌でなぞりながら、「生きていることの喜び」とはこういう状態をいうのだろうか、と自問する。それは湧き上がってくる歓喜というよりも、呼吸やまばたきや、あるいは単純な欲求を感じることなど、これまで当たり前すぎたすべてが特別なこととして認識され、それらが死と対比されることで価値として捉えられる感覚。そう、むしろ安堵感に近いのかもしれない。
生きている。確かに生きている。そして……。
「死んだら、何もない」
次に思ったのがこれだった。今回の心臓の大手術を受けての実感と言ってもいい。
手術中は心臓を止め、人工心肺装置で血液に酸素を与え、脳や体に血液を送った。自分の心臓は止まっていたわけだから、その間は「死んでいた」ともいえるだろう。
しかし、たとえば幽体離脱のような現象は起こらなかった。あっけないことに、麻酔で眠って、意識がなくなり、目が覚めたというだけのことだ。それ以上でも、それ以下でもなかった。
大きな手術ではあったが、心臓のオペは2度目ということもあって、術前から心は落ち着いていた。むしろ、魂の存在を実感できるのではないか、という期待のほうに意識が傾いていたほどだ。
でも、何もなかった。死んだら何もかも終わりなのだ。そのことが腑に落ちた。だからこそ、やりたいことはやっておかなければならない。やりたくないことに費やす時間は1秒たりともないのだ。
じゃあ、これから先、やりたいこととはなんだ。もっと病院をつくることだ。理想の病院をつくることだ。それをこの目で見届けるまで、簡単に死ぬわけにはいかない。
そこまで考えたところで、やおら強烈な睡魔が襲ってきて、再び、深い眠りの沼に落ちていくのだった。
(つづく)


